薬学はどんな学問?
薬学は、「化学物質」がどのように「からだ」へ作用するかという科学的な知見を基盤として、病気の治療や診断、予防に関する幅広い研究を通して、人類の健康増進や福祉の向上を目指す学問です。
高校までの学びから「薬学」へ
薬学の基礎となるのは、高校までの科目でいうならば化学と生物です。
加えて、物理も薬の形(剤形)を決めたりする上で大切になります。そして、論理的・演繹的思考のためには数学の素養も欠かせませんし、社会との関わりを考える上では社会科学系の知識が必要です。
最近特に重視されている対人業務を進めるためには、英語や国語などの科目を基盤としたコミュニケーション能力も非常に大切です。

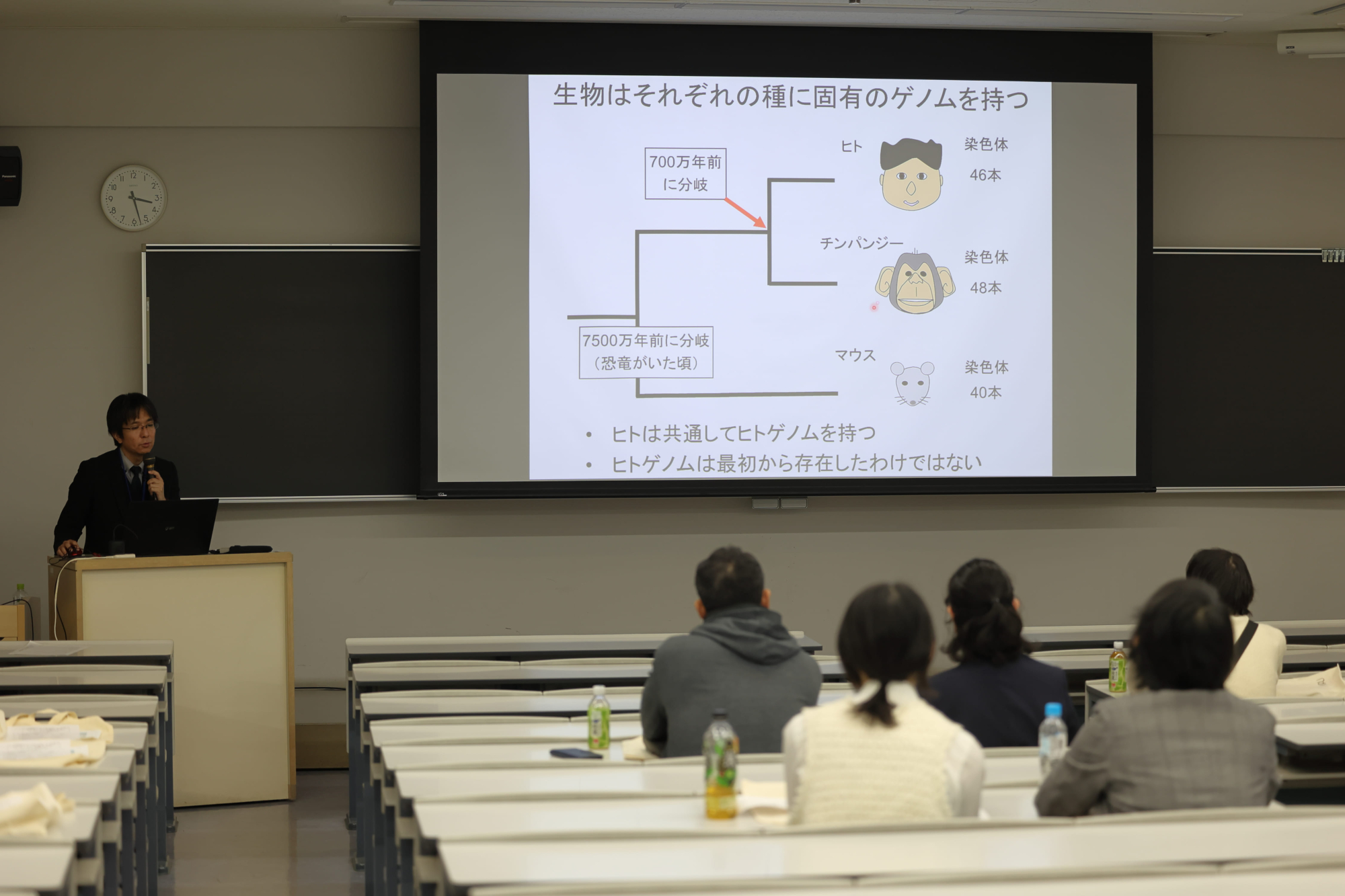
学際的な学問領域
薬学の特徴は「学際的であること」と言えるでしょう。
基礎科学の知見を活かして、病態を解明すること、治療や予防に役立つ薬の探索と作用メカニズムの研究、薬物を薬剤として人に投与できる形にすること、薬の適正使用に関する研究、薬の開発に関する社会制度に関する研究など、幅広くさまざまな分野があります。
総合的に「人の健康増進および公衆衛生と福祉の向上に寄与することを目指す学問領域」ということになります。


薬学と私たち
薬も私たちのからだも化合物でできています。
薬の作用やいろいろな病気のメカニズムを知ることで、自分自身のからだや健康のことを深く知ることができます。
薬学は、医療の進歩と発展に大きく貢献するだけではなく、有機化学のような物質を扱う分野やからだの仕組みやその異常(病態)を解明する基礎生物学分野などを含み、幅広く身近な問題を解明することを目指しており、私たち自身と深い関わりを持つ学問なのです。






