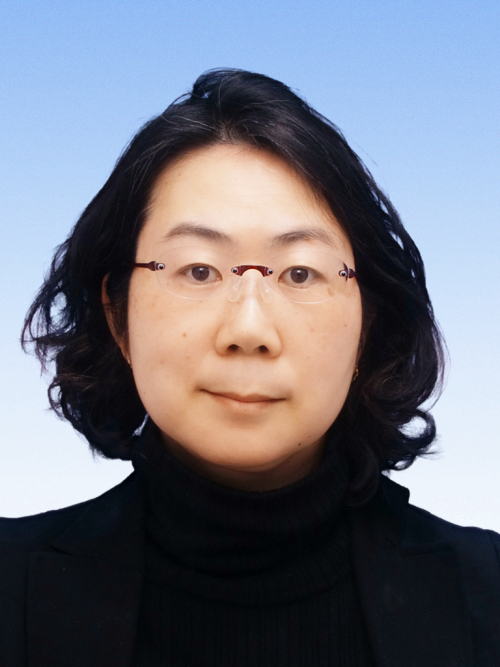病態生理学

創薬や薬物治療を行う上で、病気の原因を深く理解することは不可欠です。病態生理学研究室では、パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患や、細胞内外の水輸送を担うアクアポリンに焦点を当て、生体機能の破綻が病気の発症につながるメカニズムを分子レベルで解析しています。研究を通じて、疾患の予防戦略や治療法の確立に貢献することを目指しています。
研究室メンバー
研究テーマ
-
ドコサヘキサエン酸による中枢神経変性疾患の予防・治療効果の検討
ドコサヘキサエン酸(DHA)は脳に多量に含まれていることから、その中枢における役割が注目されてきました。特に近年では、DHAの摂取量と中枢神経変性疾患の発症率が逆相関することが明らかになってきています。当研究室では、パーキンソン病に焦点を当て、DHA投与によるパーキンソン病の予防・治療効果を検討するとともに、その作用機序の解明を目指しています。
-
神経変性疾患の病変形成メカニズムの検討
アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患の発症には、脳内でのタンパク質凝集体の異常蓄積が深く関与しています。私たちは、疾患の原因となるタンパク質の蓄積を制御する分子やシグナル経路を解析し、そのメカニズムを明らかにすることを目指しています。特に、インスリンシグナルを含む老化制御シグナルに着目した研究を行っています。
-
組織および培養細胞における水チャネルの生理学的役割に関する研究
生体内は水が占める割合が非常に高く、細胞には水を選択的に通過させる細胞膜の穴である水チャネルが存在しています。この水チャネルはアクアポリンと呼ばれるタンパク質から成ります。アクアポリンは植物、細菌、ヒトなど生物全般に存在しています。ヒトを含む哺乳類では形や性質が異なる13種類のアクアポリンが存在しています。なかでも、アクアポリン11を中心に研究を進めています。